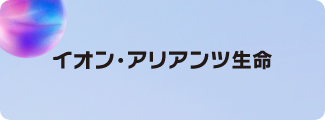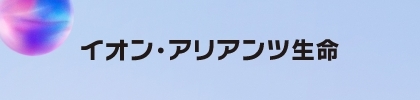痛みとかゆみがある赤い発疹 帯状疱疹の原因と症状
帯状疱疹は、従来50歳以上で増加する病気ですが、コロナ禍で免疫機能が低下する人が増加し、近年は若い世代の発症も増えているといわれています。帯状疱疹は、神経症の後遺症が残ることもあるため、症状が出たら早期に治療することが重要です。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスへの感染が原因で発症する病気です。水痘・帯状疱疹ウイルスは感染力が強いウイルスで、初めて子どもに感染し、全身に水疱(水ぶくれ)ができるのが水痘(水ぼうそう)、成人後皮膚の一部に痛みを伴う水疱ができるのが帯状疱疹です。
子どものときに水ぼうそうにかかった後、症状が改善してもウイルスは生涯にわたって神経細胞が集まっている神経節と呼ばれる場所に潜伏し続けます。そのウイルスが加齢や疲労、免疫力の低下などによって再び活動を始め(再活性化)、発症するのが帯状疱疹です。通常は、このウイルスへの初感染で発症する水ぼうそうに比べ、周囲の人への感染力は低いといわれています。
帯状疱疹の発症の原因に加齢があげられているように、年齢とともに発症リスクが高まります。ピークは70歳代といわれていますが、50歳以降で発症する人が増加することがわかっています。しかし、40歳代以下であれば発症しないということではありません。病気で免疫力が低下していたり、疲労が続いたりしていると若い世代でも発症することがあります。
成人以降の水痘(水ぼうそう)の特徴
水ぼうそうは、多くの人で子どものときに発症します。しかし、成人以降であっても水ぼうそうにかかったことがない人であれば感染することがあります。子どもの水ぼうそうは、ウイルスへの感染から2〜3週間ほどの潜伏期間を経て、赤い発疹や水ぶくれ、かゆみ、発熱などの症状が出ます。これに対して、成人以降に水ぼうそうにかかると、発疹や高熱、強い倦怠感などが現れ、なかには肺炎を起こすなど、重症化する人もいます。
帯状疱疹を発症したら早期治療が重要
帯状疱疹は、水ぼうそうにかかったことがあるすべての人にリスクがあります。ただし、水ぼうそうとまったく同じ症状が起こるわけではありません。また、生涯にわたってウイルスが再活性化することがなく帯状疱疹を発症しない人もいます。
病気や疲れなどでウイルスが活動を再開
病気や疲れなどによって免疫機能が低下すると、潜伏していたウイルスにスイッチが入り、再び活動を始めてしまいます。帯状疱疹になると、顔や身体、頭などの神経を刺激して炎症が起こることでピリピリと刺すような痛みやかゆみの症状が現れます。次第に赤い発疹が出て水疱(水ぶくれ)ができます。身体の片側の神経の走行に沿って発疹や水ぶくれができるのが帯状疱疹の特徴です。
帯状疱疹ができる部位
赤い発疹は、胸や背中、腹部などに現れることが多いですが、なかには衣服で隠れない顔や頭、耳などにも出ることがあります。また、胸や背中、腹部などに出た場合も衣服のこすれなどで痛みが増すことがあります。
帯状庖疹の治療
帯状庖疹は抗ウイルス薬で治療が可能です。抗ウイルス薬には飲み薬と塗り薬があり、飲み薬だけを処方される場合もありますが、皮膚症状によっては塗り薬を併用します。塗り薬は、水ぶくれのある皮膚を保護するために使われることもあるため、医師の指示に従って使いましょう。また、飲み薬は用量・用法を守り、処方された分を飲み切ることが大切です。痛みが強く、日常生活にも支障がある場合には鎮痛薬が処方されることもあります。
帯状庖疹は、早めに治療を開始するほど治るまでの期間が短く済みます。とくに若い世代では皮膚症状がみられても帯状庖疹を疑う人が少なく、治療が遅れる原因となります。皮膚の痛みやかゆみ、発疹は放置せず、医療機関を受診することが重要です。
帯状疱疹の後遺症とは
帯状疱疹は、水ぶくれが次第にかさぶたになって症状が改善していきます。皮膚症状が治れば痛みも治まりますが、なかには皮膚症状が治まった後にも痛みが残ることがあります。これを帯状疱疹後神経痛(PHN)といいます。帯状庖疹の後遺症でもっとも頻度が高いもので、3か月で7~25%、半年後でも5~13%の人に痛みが続くという報告があります※1。
帯状庖疹後神経痛は、ウイルスによって神経が傷つけられてしまうことが原因と考えられています。帯状庖疹後神経痛になると治療が長期化し、痛みが取り切れないこともあります。
帯状疱疹のワクチンは50歳から
帯状庖疹は、近年若い世代にも増えているといわれています。その原因のひとつと考えられているのが、小児の水痘用ワクチンが定期接種化され、水痘(水ぼうそう)を発症する子ども自体が減ったためです。いまの成人以降の多くの人は、子どものころに水ぼうそうにかかっており、ウイルスを持っています。これまでは、その人たちの子どもが水ぼうそうになったときに保護者として看病する際に、ウイルスに対する免疫が強化されて帯状庖疹の発症を防いでいましたが、免疫が再強化される機会がなくなったことで、子育て世代にも増えている可能性があるのです。
ワクチンでの予防
水痘・帯状疱疹予防ワクチンには、弱毒生水痘ワクチンと、組換え帯状疱疹ワクチンの2種類があり、小児の水痘予防には弱毒生ワクチンが、成人の帯状疱疹予防には弱毒生水痘ワクチン、あるいは組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかが用いられます。
2014年10月から小児用の水痘ワクチンが定期接種化されていますが、定期接種を受けていない人で水ぼうそうにかかったことがない人は、水痘ワクチンの接種を検討しましょう。定期接種対象外の人は自費になりますが、ワクチン接種を受けることは可能です。とくに妊娠中に水ぼうそうにかかると、手足や目の症状、水頭症などの神経障害がみられる先天性水痘症候群のリスクがあります。
妊娠を考えている人で水ぼうそうにかかったことがない人は、妊娠前に抗体検査を受け、抗体がない場合にはワクチン接種を受けておくと安心でしょう。子どものときに水ぼうそうにかかったことがある人は、基本的には水痘ワクチン接種の必要はないとされています。
帯状庖疹ワクチンとは?
水ぼうそうにかかったことがあったり、水痘ワクチン接種を2回受けている人は水痘・帯状庖疹ウイルスに対する免疫を獲得していますが、年齢とともにその効果が弱くなっていきます。
加齢などによって免疫機能が低下すると帯状庖疹を発症しやすくなるため、50歳以降の人は帯状疱疹ワクチンの接種対象となっています。また、18歳以上で、移植手術を受けていたり、抗がん剤治療を受けていたりする人なども帯状疱疹ワクチンの接種対象となっています。
2025年4月からは、65歳以上の人で帯状庖疹ワクチンの定期接種化が始まります(60歳以上の特定の疾患などの人も対象)。帯状庖疹はワクチンによって予防ができる病気です。帯状疱疹は、発症するとつらい後遺症に悩まされる可能性があります。水ぼうそうにかかったことがある50歳以上の人は接種を検討してみましょう。
ここがポイント!
・帯状疱疹は、水ぼうそうの原因ウイルスである水痘・帯状疱疹ウイルスの活性化が原因
・帯状疱疹は、顔や身体、頭などの神経を刺激して刺すような痛みやかゆみが出て、赤い発疹、水ぶくれができる
・発疹が治まっても痛みが続く帯状疱疹後神経痛(PHN)の後遺症が出ることがある
・抗ウイルス薬の内服や塗り薬で治療でき、痛みが強い場合は鎮痛薬を使うこともある
・水ぼうそうにかかったことがない人は、定期接種対象外でも水痘ワクチンを自費で接種できる
・帯状疱疹ワクチンは、50歳以降(リスクがある18歳以上)で接種できる
・2025年4月からは65歳以上の人の定期接種化が開始される
<参考資料>
※1 Thyregod, H.G. et al.:Natural history of pain following herpes zoster. Pain, 128(1-2):14-156, 2007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17070998/
(2025年3月14日閲覧)
・国立感染症研究所:水痘とは
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/418-varicella-intro.html
(2025年3月14日閲覧)
・厚生労働省:予防接種・ワクチン情報
(2025年3月14日閲覧)
・厚生労働省:第21回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会 資料 帯状疱疹ワクチンについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001165467.pdf
(2025年3月14日閲覧)
・厚生労働省:令和6年度第4回予防接種自治体向け説明会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50211.html
(2025年3月14日閲覧)

宮崎滋
(みやざき しげる)
公益財団法人結核予防会総合健診推進センター所長
https://www.ichiken.org/
東京医科歯科大学卒業後、都立墨東病院、東京逓信病院等勤務を経て、2004年に東京医科歯科大学臨床教授に就任。以降、東京逓信病院副院長、新山手病院生活習慣病センター長を歴任し、2015年より現職。日本医学会評議員をはじめ、日本内科学会、日本肥満学会(名誉会員)、日本糖尿病学会(功労評議員)、日本生活習慣病予防協会(理事長)、日本肥満症予防協会(副理事長)などを務めている。