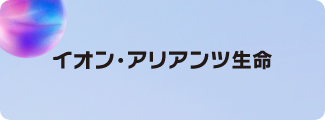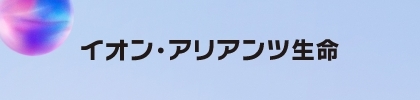更年期以降でリスク増大 LDLコレステロールが高いとどうなる?
女性は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少に伴い、閉経以降で脂質異常症の人が急激に増えることがわかっています。これに加え、中高年以降のライフスタイルの変化も脂質の上昇には影響していると考えられます。動脈硬化の原因となり、将来的な心筋梗塞や脳梗塞、認知症などの予防のポイントにもなる女性の脂質異常症を防ぐポイントについてご紹介します。
脂質のコントロールにも関与する女性ホルモンの役割とは
女性ホルモンのエストロゲンには、脂質や血圧、内臓脂肪を抑制して肥満を防ぐ作用があります。そのため、若年層の女性は男性に比べて脂質異常症の人の割合が非常に低くなっています。しかし、女性のLDLコレステロールは更年期前後で大きく変化します。閉経とともに女性ホルモンが減少すると内臓脂肪型肥満になりやすく、それに伴って血管の動脈硬化が進み、血圧も上昇しやすくなります。
脂質異常症が疑われる人の割合は閉経前後の50歳代から急激に増加します。60歳代に入ると男性を上回り、70歳代以上では40%を超えます。
エストロゲンの作用が減少すると……
女性ホルモンであるエストロゲンの脂質に対する直接の作用はLDLコレステロールのみといわれていますが、脳や神経に働きかけて食欲を抑えたり脂肪の代謝を促したりすることによる間接的な作用もあります。
これによって内臓脂肪の蓄積や肥満が抑えられるため、LDLコレステロール以外の脂質の上昇も防ぐ効果が期待できるのです。
しかし、閉経前後からエストロゲンの分泌量が減少することで、脂質を抑える作用が弱くなります。エストロゲンは男性の体内でも合成されていますが、女性に比べると非常に量は少なく、その作用による脂質の抑制効果は限定的ですが、閉経後は男女の差がなくなってしまうというわけです。そのため、食事から摂った脂質がLDLコレステロールの上昇、内臓脂肪の蓄積に直結してしまい、女性の脂質異常症の増加につながります。
“薬で補充”では心筋梗塞の予防効果はない?
ホルモン補充療法(HRT)は、減少するエストロゲンを補うもので、更年期の多様な症状を軽減する治療法です。エストロゲンの減少が脂質の上昇などに影響するのであれば、エストロゲンを補うことで冠動脈疾患の予防につながることを期待したいところです。しかしこれまでの研究で、体内で分泌されるエストロゲンとは異なり、外からエストロゲンを補っても冠動脈疾患の発症を抑える効果を期待することができないことがわかっています。そのため、ホルモン補充療法はあくまでも更年期障害の症状軽減を目的に行うものであり、脂質や冠動脈疾患の予防を目的にすることは推奨されていません。
大事なのは早期診断、治療
男性は若いうちから食生活の乱れや運動不足などによって脂質が徐々に上昇するのに対し、女性はエストロゲンの影響が弱まる更年期を迎えるころから急激に脂質が上昇しやすくなります。生活習慣そのものが閉経前後で大きく変わらなければ、脂質を気にすることもないでしょう。しかし、本人も知らないうちに脂質異常症になっていることが多いのです。健康診断ではとくに脂質の変化に注意して、食事や運動の見直しを進めていきましょう。脂質が基準値を超えたら脂質を下げる薬が必要になることもあります。
更年期世代で、喫煙習慣や糖尿病、高血圧などの生活習慣病がある場合は、かかりつけの婦人科で相談したり、循環器内科を受診したりと、早めの対応が重要です。
注目したい運動量の変化
脂質の上昇を抑えるためには、禁煙、適正体重の維持、栄養バランスのよい食事、塩分を控える、飲酒過多にならないように注意する、適切な運動を習慣化するなどの対応が必要です。
平均年齢が高い女性の生活習慣病予防
女性は男性に比べて平均寿命が6~7年長くなっています。更年期以降の人生も長いため、いかに健康で長生きできるかが重要となります。脂質異常症は、動脈硬化を進行させる大きな原因で、動脈硬化が進行することで脳卒中のリスクが高まり、それがもとで脳血管性認知症を起こすことがあります。また、動脈硬化はアルツハイマー型認知症のリスクにもなることがわかっています。
認知症は要介護の最大のリスクであり、健康的な生活を送るうえでの大きな障害となるものです。健康で長生きするためには認知症の原因にもなる動脈硬化を防ぐことが重要であり、脂質をコントロールすることは動脈硬化の予防にとって欠かせないものといえます。
活動量の見直しがポイントに
仕事や家庭に多忙な毎日を過ごしていた人も中高年以降は少しずつ子育てが終わっていき、経済的にも若年層に比べて余裕がある人が増えていきます。その一方で日常生活での活動量は徐々に減っていきます。
活動量の減少は、フレイルやサルコペニアの原因となり、女性の場合は閉経によって骨密度が低下して骨粗鬆症リスクも高めます。フレイルやサルコペニア、骨粗鬆症からの骨折は認知症と同様に要介護のリスクです。運動を習慣化することは、脂質の上昇を抑えたり血管のしなやかさを保ったりするだけでなく、骨を強くして骨折リスクを防ぐなど、さまざまな要介護リスクへの備えとなります。
脂質異常症を予防するための運動
脂質異常症を予防するための運動は、血液中の脂質改善効果を得る中強度以上の有酸素運動を中心に行うのがよいとされています。定期的に行うことが重要なため、毎日30分以上を目標にしましょう。そのうえで自分の体重などで負荷をかけるレジスタンス運動を行うことが効果的です。
ここがポイント!
・女性ホルモンのエストロゲンには、脂質や血圧、内臓脂肪を抑制して肥満を防ぐ作用がある
・閉経前後で脂質、とくにLDLコレステロールが急激に増加する女性は多く、動脈硬化やそれに伴う脳心血管の病気の原因となる
・更年期障害の治療であるホルモン補充療法は、脳心血管の病気の予防のみを目的として行うことは推奨されていない
・中高年以降は運動量も減少するため、積極的に運動し、食事面でも工夫しながら脂質を管理することが重要
<参考資料>
・女性の健康とメノポーズ協会:女性の健康について 更年期以降に起こる疾患 閉経後に気を付けたい脂質異常症
https://www.meno-sg.net/health/disease/249/
(2025年4月15日閲覧)
・健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~ 生活習慣病などの情報 e-ヘルスネット: 栄養・食生活 病気の予防・治療と食事 脂質異常症(基本)
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-02-012
(2025年4月15日閲覧)
・健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~ 生活習慣病などの情報 e-ヘルスネット: 身体活動・運動 疾病の予防・改善と運動 脂質異常症を改善するための運動
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/exercise/s-05-003
(2025年4月15日閲覧)
・骨粗鬆症財団:骨粗鬆症とは 栄養と運動
https://www.jpof.or.jp/osteoporosis/tabid270.html
(2025年4月15日閲覧)

吉丸真澄
(よしまる ますみ)
吉丸女性ヘルスケアクリニック院長
https://yoshimaru-womens.com/
金沢大学医学部卒業後、国立病院機構東京医療センター、東京歯科大学市川総合病院に勤務。2012年に東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教に就任。2020年に吉丸女性ヘルスクリニックを開業。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医、日本抗加齢医学会認定抗加齢専門医、日本医師会認定健康スポーツ医、NR・サプリメントアドバイザー